風流人
佐久間吉太郎 (1874–1955)
高橋勝子
日本美術展
Seattle Art Walk at 84 Yesler


Greeting


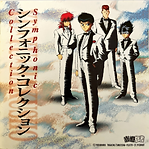

皆さん!風流人、佐久間吉太郎の世界にようこそ!
佐久間吉太郎(1874-1955)は明治、大正、昭和の時代に侘び寂びの世界に生きたわたし達の風流人祖父です。
祖父は明治、大正、昭和の時代、西暦で言うと1874年から1955年に生存しました。侘び寂びの世界で生きた絵描きであり能や謡曲の師匠でもありました。彼が残した彼の絵と遺品を今日ここパイオニア・スクウエァで皆さんに見て頂ける事を光栄に思います。
これらの数々の絵や江戸時代の書籍等は母が亡くなって家の片ずけをした時に天井裏から出て来ました。おそらく祖父が亡くなって以来この古い箱に眠っていた物です。私は祖父や両親の遺品と共にシアトルに持ち帰りました。
私は子供の頃に祖父の家で家族と共に祖父が亡くなる前の5年間を一緒に生活しました。藁葺の家と四季ごとに花が咲く庭は今思えば侘び寂びの世界でした。祖父は寒い雪の降る日に家の障子を開けて庭を眺め幼い私に『勝子さんや!風流じゃの〜!』と言っていました。その声は今も思い出されます。
展示している絵は殆どが練習用に描かれた物です。当時和紙が高価だったので何枚も紙を貼り合わせています。同じ紙に違った絵、向きを変えて空いたところに絵が描かれています。一度描き始めると消せない為はみ出した部分には紙を足しています。何度も何度も同じ絵を描いていた事がわかります。祖父の絵にはユーモアがあります。動物は笑っています。戦いに行く武士までが春の花を見つけて微笑んでいます。祖父の絵は江戸時代の庶民の生活模様、人物動物等素朴な様子が描かれています。動物や人の命を描こうとしました。100年後の今も絵はくちる事もなく色も変色していません。絵を一枚一枚私自身が額に入れました。
祖父の遺品の書冊の何冊かは江戸時代に出版された物である事を最近知りました。江戸時代の書物は主に木版印刷でした。板木に文字や絵を彫り墨をつけて紙に印刷する方法で絵師、彫師、摺師という分業体制が確立されていました。全てが手仕事でした。こんなに詳細によく彫れたものだと感心しています。
残念ながら祖父の事は私の思い出とこの絵や遺品以外の事はわかりません。
ちなみに祖父の繊細な感性は孫のボブ佐久間に引き継がれています。彼は日本で昭和、平成そして令和の今も作曲編曲家として又シンフォニーの指揮者として活躍しています。私自身といえば例えば冬の終わりの枯れた草花の間に咲くスミレの花にようやく春が来たと感じたり未完成の中にある美しさ古い物と新しい物との調和を家のインテリアや庭に生かしています。又私はこの84イエスラーレストランのオーナーでありインテリアは私の感性と趣きです。
出来るだけ祖父の絵に近づいて詳細な描写を見てお楽しみ下されば幸いです。虎の絵に三日月が描かれているのがわかりますか?武士が笑って見ている物は何でしょう?などなどお楽しみください。
本日はご観覧頂き誠に有難う御座いました。
2025年9月4日
高橋 勝子

Edo–Meiji Art Books



和本とは、近代の印刷技術が普及する以前に作られた日本の伝統的な書籍を指します。手漉きの和紙を用い、糸で綴じられた装丁が特徴で、優美な書や豊かな挿絵を備えています。内容は古典文学や能の謡本、美術の手本集や百科事典まで多岐にわたり、その時代の美意識や学問、生活を映し出しています。
以下に挙げるのは、本展でご紹介している作品の一部です。ただし、時代の古さや限られた知見のため、詳細が判明していないもの、正確な情報が特定できないものも含まれています。それでも、これら一冊一冊が日本の文化遺産として大きな価値を持ち、当時の文学や美術を知る貴重な手がかりを与えてくれます。
-
『和漢名筆金玉画府』(1771年刊)
日本と中国の名筆・名画を集めた豪華な手本集。全6巻。
当時の学習者が書や絵を練習する際に広く利用されました。
書の部は唐代・孫過庭の『書譜』に基づき、理論と手本を兼ね備えた内容で、
絵の部は名画を集めた「画寶」として、弟子が模写して学ぶために活用されました。
-
『光悦本 高砂』
本阿弥光悦(1558–1637)の書風で書かれた謡本。
演目「高砂」は、夫婦和合と長寿を祝う能で、婚礼でも謡われるおめでたい曲。
書と能楽の両面から、日本文化の象徴的存在といえます。
-
『古今著聞集』
鎌倉時代に橘成季が編んだ説話集。神仏、武士、芸能、世俗の逸話を収録。
『今昔物語集』『宇治拾遺物語』と並ぶ代表的説話集で、後世の文学・芸能に大きな影響 を与えました。
-
『故牘談 乾』
古文書や手紙をもとにした逸話集。「乾」は第一巻を意味します。
江戸時代に流行した「談義本」の一つで、昔の事件や人物談をまとめています。
-
『道中馬譜 全』
街道を旅する際に使われた馬の種類や特徴を記録した資料。
馬は輸送・交通の要であり、各地の産地や血統を整理したものは、武士や商人にとって 重要でした。
-
『六書通』
漢字の成り立ちを六つの原理(象形・指事・会意・形声・転注・仮借)に基づいて解説した学習書。江戸時代の知識人が漢字の理論を学ぶための必読書でした。
-
『名家画譜』
有名画家の作例を手本として収めた画譜。
草花・鳥獣・山水・人物など多彩な題材が収められ、弟子や愛好家の練習用に用いられ ました。
-
『本朝画苑』
「本朝」とは日本のこと。江戸後期に編まれた画史書で、日本の画家の伝記や作品を整理したもの。中国の画史を模範としつつ、日本独自の画家の系譜を記録した貴重な資料です。
-
『一筆画譜』
筆を離さず、少ない筆遣いで形をとらえる描法を集めた手本集。
花鳥・草木・人物・動物などを数筆で簡潔に表現する技法が紹介され、庶民や子供にも人気がありました。

